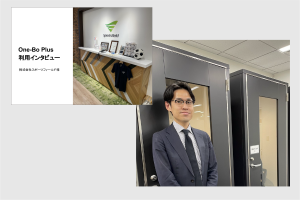近年、雇用の現場では「ジョブ型雇用」という言葉を耳にする機会が増えてきています。同制度は、日本で定着している従来の雇用システムとは大きく異なり、複数の大企業が導入を推進していることも影響して大きな関心が寄せられています。今回はこのジョブ型雇用についてわかりやすく解説します。
テレワークなど、新しい働き方の普及で注目を集める「ジョブ型雇用」とは?

テレワークなどの新しいワークスタイルの浸透に伴い、ジョブ型雇用への注目が集まっています。ここでは、ジョブ型雇用の特徴と従来の雇用スタイルとの違い、現在関心が高まっている理由などについて解説します。
ジョブ型雇用は、職務の内容に基づいて必要なスキルを持った人材を採用する制度
ジョブ型雇用とは、各職務の業務内容を「職務記述書(ジョブディスクリプション)」で明確に定義し、その業務内容にマッチした知識やスキル、経験を持つ専門性の高い人材を採用する雇用システムです。職務記述書に記載されていない業務を行うことは契約違反にあたり、他の従業員の仕事を奪うことにもなるため原則として禁止されます。
企業において必要な職務と人数はあらかじめ決まっており、欠員が出たり、新規事業で人材が必要になったりしたタイミングで募集がかけられます。つまり、仕事ありきでそこに見合う人材を雇う、仕事に人を割り当てるというのがジョブ型スキルの考え方です。
これは新卒を一括採用し、入社後に個人の適正に合わせて配属先を決定する従来の日本の人事システムとは大きく異なります。
ジョブ型雇用では始めから職務にマッチする人材を雇うため、「事務職から営業職に異動になった」といったジョブローテーションは行われません。アメリカやヨーロッパでは一般的なシステムですが、日本人にとっては馴染みが薄く社会的な理解も進んでいないため、自社で導入する際は慎重に検討する必要があります。
今、ジョブ型雇用が注目されている理由
急激に注目度が高まっている背景には、新型コロナウイルスの感染拡大に伴うテレワークの普及や、国際競争力を強化する必要性、少子化による人材不足、働くことに対する価値観の多様化などがあります。特に大きいと考えられるのが、新型コロナウイルスの感染拡大による影響です。テレワークに代表されるように、これまでとは異なる働き方を余儀なくされている企業も少なくないでしょう。
従業員全員がオフィスに集まりにくい状況の中では、これまでのように勤務態度などの定性的な基準で個人を評価するのは難しく、どうしても成果重視にならざるを得ません。そこで成果を評価対象とするジョブ型雇用の方が、テレワークとの相性が良いとする考え方が広まってきています。
また、日本の採用システムでは、ジョブ型雇用が一般的な諸外国と比較して専門的なスキルを持った人材が育ちにくい傾向にあります。さまざまな職務の経験によって一人ひとりの総合的な能力は高まるものの、企業の国際競争力に貢献するような専門分野に特化した人材を生み出すのは難しいのが実情です。
特に今後はIoTやDXのさらなる加速に伴い、ITの知識やスキルを持った専門的な人材を確保することが一層重要になってきます。しかしながら、日本では現在IT人材不足が深刻化しており、少子化の影響もあって将来的にはさらなるIT人材の不足が懸念されている状況です。そこでジョブ型雇用を導入し、ITのスペシャリストを確保しようとする機運が高まっています。
近年、さまざまな働き方を柔軟に取り入れるダイバーシティの価値観が広がりつつあることも、ジョブ型雇用が脚光を浴びるようになった理由の一つといえます。ジョブ型雇用では勤務地や勤務時間が制限されるため、高度なスキルがあるにも関わらず、これまで育児や介護との両立が難しいために働けなかった人材の採用も可能となるのです。
従来の「メンバーシップ型雇用」とジョブ型雇用の違い

日本で普及している雇用システム「メンバーシップ型雇用」とジョブ型雇用は具体的にどう違うのでしょうか。それぞれを比較してみましょう。
そもそも「メンバーシップ型雇用」とは
メンバーシップ型雇用とは、ジェネラリスト型の人材を長期的に育成していくことを前提とした雇用システムです。職種や勤務エリアが流動的な「総合職」はその最たるものといえます。
日本企業の多くは職種を限定せずに新卒採用を行い、入社後の研修や面談で社員の適性を見極めて配属先を決めます。ジョブ型雇用のように入社前の段階で職務の詳細がしっかりと明示されるのは稀なケースでしょう。
採用後はジョブローテーションによって総合的な能力を養い、長きにわたり会社に貢献する人材へと育成していきます。就職というよりも就社に近く、ジョブ型雇用と比較すると専門スキルが育ちにくいのがネックとされています。
しかし、年次が上がるに連れて昇給・昇格の可能性が広がるなど、長く勤めるメリットが用意されており、安定して働けるところが魅力といえるでしょう。ジョブ型雇用を採用する企業も増えつつあるとはいえ、現在の日本社会においてはやはりメンバーシップ型雇用が主流です。
ジョブ型雇用とメンバーシップ型雇用の違いは主に「職務範囲」と「評価方法」にある
両雇用システムの大きな違いとして挙げられるのは、職務の範囲と評価基準の2点です。ジョブ型雇用はスキルありきで採用するため、あらかじめ職務記述書で業務範囲が明確に定められており、それ以外の仕事をする必要はありません。
勤務地も限定されており、原則として異動や転勤などの配置換えもありません。スキルアップへの取り組みは個人に任されている場合が多く、必要なスキル・知識を自分から積極的に習得する主体性が求められます。
一方でメンバーシップ型雇用は、社会経験を持たない新卒のポテンシャルを評価して採用するため、入社時点では職種や配属先が決まっていない場合がほとんどです。転勤や配置換えもあり、人に仕事を割り当てるため担当職務の範囲は限定されていません。企業側には長期にわたって社員を育成する目的があり、入社時だけでなく定期的に研修が用意されています。
この2つは評価基準も異なります。ジョブ型雇用は、個人の能力と決められた業務に対してどれだけの成果を挙げたかによって評価が変動します。
対するメンバーシップ雇用は、年齢や勤続年数といった成果以外の要素も評価に加味されます。実力主義の企業が増えたとはいえ、やはり勤続年数の長い社員や上司と良好な関係を築いている社員が出世する風潮が残っています。
自社に合うのはどっち?ジョブ型雇用とメンバーシップ型雇用それぞれのメリット・デメリット

ジョブ型雇用もメンバーシップ型雇用も、どちらかが優れているというわけではなく、両者にメリットとデメリットがあります。それぞれを比較して自社に合ったやり方を見極めることが重要です。以下で詳しく解説します。
ジョブ型雇用のメリット
スペシャリストが確保できる
最大のメリットは、やはり専門性の高い人材を採用できる点にあります。職務内容に合ったスペシャリストを迎えられるので、企業の生産性の底上げが期待できるでしょう。あらかじめ業務内容を明確にしているため、入社後のミスマッチの防止も期待できます。
従業員としても、転勤や配置換えの心配がなく、自分の専門分野に集中しながら腰を落ち着けて働けるのは大きなメリットの一つです。
テレワークに適している
成果を軸として従業員を評価するため、今後定着化が予想されるテレワークに適している点も特徴です。ただし、そのためには透明性が高く従業員が納得できる評価基準を設定する必要があります。
ジョブ型雇用のデメリット
従業員の配置換えができない
数多くのメリットがある一方で、ジョブ型雇用ならではのデメリットも存在します。企業は原則として従業員の配置換えができず、人員不足の部署の人員を削減する、強化したい部署の人員を増やすといった会社都合の調整が難しいという特徴があります。
優秀な従業員が転職しやすい
さらに、ジョブ型雇用では終身雇用を前提としていないため、優秀な従業員により条件の良い企業に転職されてしまうリスクを抱えることとなります。欠員が出たところで、前任者と同等のスキルを持つ後任者がすぐに見つかるとは限りません。
働く側としては、景気や会社の都合で自分のポジションがなくなってしまった際、社内の空いているポストに異動するという選択肢がないため、新しい仕事先を探さなければならない不安があります。どこに行っても通用する人材になるためには、常に研鑽を続けなければならないというプレッシャーもあるでしょう。
メンバーシップ型雇用のメリット
長期的な人材育成が可能
日本人にとってなじみ深いメンバーシップ型雇用の大きなメリットとしては、帰属意識の高い社員を育成しやすく、長期にわたって会社の発展に貢献してもらえる点が挙げられます。一つの会社で長く働くことを前提としているため人材が定着しやすく、安定した人材基盤を形成できます。また、欠員の発生や人員の増強、新規事業の立ち上げに際して社内の人材を適切に配置できるなど、状況に応じた柔軟な人事異動が可能です。
従業員は会社都合で突然解雇されるリスクが少なく、仮に担当領域の仕事がなくなってしまったとしても、配置換えによって同じ会社で働き続けることができます。研修や教育制度が充実している企業であれば、初めて取り組む仕事でも少しずつ覚えながらステップアップしていけるでしょう。
視野の広いゼネリストが育成できる
ジョブローテーションによって幅広い業務に触れる中で自分に適した仕事が見つけやすく、視野の広いゼネリストを育成できる点も利点の一つです。
メンバーシップ型雇用のデメリット
スペシャリストが育ちにくい
幅広い業務を経験させることで総合的なスキルを持った人材を育成できる一方、専門分野を極めたスペシャリストが育ちにくいというデメリットがあります。特にITなどの専門分野では、十分な教育体制が整えられないために人材不足に陥りがちです。自社だけでは必要な人材を確保できず、外部のリソースに頼らざるを得ない企業も多いでしょう。
長期勤務の従業員が増えるほど人件費が増える
基本的には年次とともに給与水準が上がっていくため、長期勤務の従業員が増えるほど人件費がかかります。会社への貢献度が低い従業員に対しても高い給与を支払っているケースは少なくありません。
従業員としては、ジョブローテーションによって希望しない職種や部署へ異動になるデメリットがあります。やりたい仕事をさせてもらえない状況にストレスを感じる場合もあるでしょう。
ジョブ型雇用の導入にあたり、企業が押さえるべきポイントと注意点

これからジョブ型雇用の導入を検討しているのであれば、いくつか押さえておくべきポイントがあります。事前に対策しておきたい内容についてまとめました。
「職務記述書(ジョブディスクリプション)」の作成
ジョブ型雇用は仕事ありきの採用なので、導入にあたり職務記述書の作成が必須です。職務記述書とは、企業が募集しているポジションの職務内容や、それを遂行するために必要なスキル、仕事の条件などを細かく定義した書類です。企業と応募者は職務記述書に記載された内容に沿って契約を結ぶため、内容を吟味して慎重に作成しなければなりません。
しかし、いきなり雇用システムを完全にジョブ型雇用に切り替えるのは困難を極めます。新卒を総合職として採用しているケースでは、職務の内容が明確化されていない場合も少なくありません。
総合職の業務内容や業務範囲をはっきり定義するとなれば、時間も手間もかかりすぎてしまいます。そのため、まずは一部の業務を対象にスモールスタートしてみるのも一つの手です。
内容を定義しやすい定型の業務や、マネジメント職といったポジションから、通年のジョブ型採用に取り組んでみてはいかがでしょうか。
ジョブ型雇用に合わせた評価基準の設定
ジョブ型雇用のメンバーを社内に迎えたり、会社として制度を変更したりするにあたり、明確な評価基準の設定が欠かせません。まずは職務に求める役割や、昇格や給与アップの基準、評価で重視する点などを明らかにしてください。報酬についても、人材市場全体の水準に照らし合わせて決定する必要があります。
また、それをすべての社員やスタッフに理解してもらうことが大切です。評価の基準に透明性がない場合、メンバーシップ型で雇用されている従業員に納得してもらうのは不可能です。ジョブ型雇用のメンバーに対して不公平感を抱いて会社へのロイヤリティが低下し、手塩にかけて育成した社員が外部に流出する恐れもあります。
労働組合など、従業員への十分な説明
社内の制度自体をメンバーシップ雇用からジョブ型雇用へと移行する場合、労働組合の理解を得ることも欠かせません。職務記述書を作成する段階で団体交渉を要求される可能性があります。また、その職務が不要になった場合は整理解雇もやむを得ない以上、ジョブ型雇用の導入そのものに反対されるかもしれません。
従業員としても、終身雇用を前提に働いてきた立場から「解雇されてしまうかもしれない」という不安感は大きいでしょう。それらを払拭してモチベーション高く働いてもらうためにも、労働組合や従業員への説明を丁寧に行う必要があります。不安要素だけでなく「専門性を深められる」などのメリットについても伝えましょう。
会社と従業員の間で制度への認識齟齬を避けるための取り組みも徹底しましょう。雇用形態の一種としてジョブ型雇用を採用する場合、具体的な規定を定めて就業規則に記載し、誰でも確認可能な状態にしておくことがトラブル回避につながります。
人事施策の見直しなどにより、従業員のワークエンゲージメントを向上させる
仕事ありきのジョブ型雇用では、会社への帰属意識の低さが問題になりやすい側面があります。働き手にとっては、より労働しやすい条件を求めて勤務先を変えるのは当然のことです。
そのため、企業側には「この会社で働きたい」という気持ちを高めるための工夫が求められます。自社ならではの福利厚生や、そこでしか経験できない仕事など、会社としての魅力をより強める施策を実施しましょう。
また、ジョブ型雇用は、従来の人事制度や社内規則とのミスマッチが懸念されます。ジョブ型雇用のメンバーにやりにくさを感じさせないためにも、制度や規則の練り直しが必須です。
どう取り入れている?日本におけるジョブ型雇用の導入事例

日本ではまだ一般的ではないジョブ型雇用ですが、大手企業ではすでに導入が進んでいます。ここからは先行企業の導入事例をご紹介します。
【日立製作所】国や場所、時間に捉われない働き方の実現を目指した事例
総合電機メーカーの日立製作所は、2021年4月から「ジョブ型人財マネジメント」の運用をスタートすると表明し、注目を集めています。将来的には国内で働く16万人を含め、世界中の従業員30万人にこの制度を適用する計画です。
新制度運用のための仕組みは2024年をめどに整備するといい、各職務の内容を明確にした職務記述書はおよそ300~400種類にも及ぶとされています。すでに管理職や海外拠点ではジョブ型雇用を導入しており、世界規模で人事ルールを揃えるための試みとして計画されました。
社員の主体性を向上させて意欲的にキャリア形成に取り組んでもらうことで、会社全体の生産性や競争力を高める狙いもあるようです。
【富士通】まずは管理職からジョブ型雇用を採用した事例
総合電気メーカーの富士通も大胆な人事制度改革に乗り出した企業の一つです。同社では2015年より、幹部社員の一部を対象に職責を7段階に分け、報酬もそのランクに紐づける「FUJITSU Level」というジョブ型人事制度を採用してきました。
2020年4月には国内の管理職約1万5,000人にもジョブ型の人事制度を拡大しています。評価は職務記述書に明示されている役割を全うしたかどうかに重きが置かれ、月給が固定されている分、成果に基づいて賞与・インテンティブを付与します。
なお、一般社員のジョブ型雇用については、労働組合との対話を重ねた上で、数年後のスタートを目指しているそうです。
【資生堂】企業独自のジョブ型雇用を導入した事例
国内の大手化粧品メーカー資生堂は、企業独自のジョブ型雇用を展開しています。同社は2020年1月、国内の管理職のうちおよそ1,700人を対象に「ジョブグレード制度」を導入しており、2021年からは一般社員およそ3,800人にも広げる計画です。
導入の背景には、国際的な競争力の強化の狙いがあります。同社は競合である外資系化粧品メーカーと比較した際、従業員一人あたりの生産性が低く、さらに同じグループの海外拠点のメンバーと比べた場合にも、専門性に乏しい従業員が多いことが課題でした。
同社のジョブ型雇用は、ジョブファミリー(領域)ごとに職務記述書を作成し、1つのジョブファミリーの中で働くことを前提に従業員の採用や教育を行うというものです。ジョブファミリーの中には職務等級が設けられており、その中で昇進しながら専門性を高めることができます。また、ジョブを細分化しすぎないことで配置換えにも対応でき、チームワークを保てるという独自の方針を打ち出しています。
会社に合った雇用形態を検討しよう

「ジョブ型雇用」は、職務内容を職務記述書に明示し、その役割に見合う人材を採用する雇用システムです。配置転換によってジェネラリストを育てる従来の「メンバーシップ型雇用」と異なり、専門性の高いスペシャリストを採用・育成します。
現状では一部の大手企業でしか導入が進んでいないものの、テレワークの普及や少子化に伴う人材不足などが追い風となり、今後さらに浸透していくことが予想されます。両者を比較し、自社に最適な雇用システムのあり方を検討してみてください。